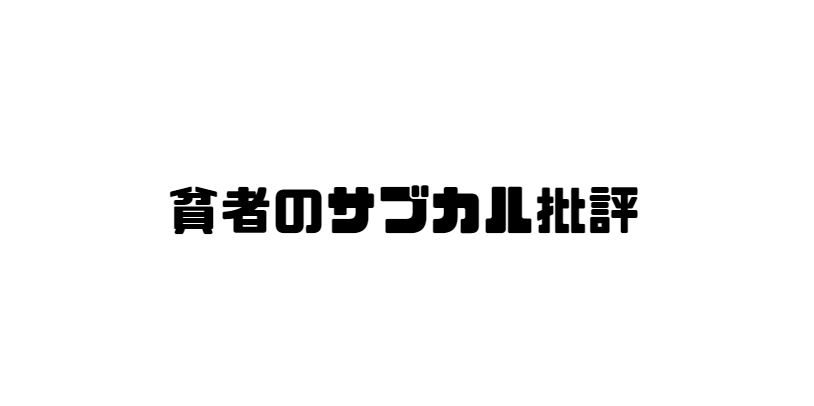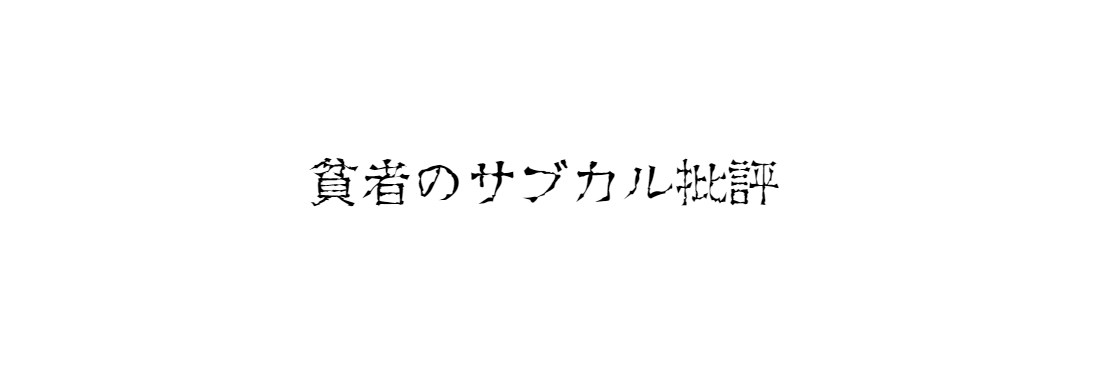※ネタバレを含みます。
【 「センスの人」でありたい男の哀れな足掻き 】
それにしても西野亮廣は嫌われている。彼が新興宗教のような活動を始める前から、特にネットの世界において彼の受け入れられなさは群を抜いている。確かに面白くない上に独特の気持ち悪さを持ってはいるが、それにしても叩かれ過ぎである。一体人々は彼の何をそんなに受け入れられないのか。
「えんとつ町のプペル」は挑戦する度に世間から攻撃され続けた西野の悲痛な叫び、その具現化である。映画を観る限りどうやら世間からのバッシングの一言一言はしっかりと彼に刺さっていたようで、自分の象徴であるルビッチに向けて町の人が放つ心無い言葉は、彼のアンチがネット上で使う言葉そのままだ。私はハートの強い彼にアンチの言葉が効いていたという事自体に大変な衝撃を受けたのだが、それを自身の手掛ける作品に何の手心も加えずそのまま流用する節操の無さにはもっと驚いた。彼は「作り手は映画にメッセージを込めるもの」という聞きかじった情報を極めて私的に、極めて利己的に解釈して利用したのだ。
「映画にメッセージ性を持たせる」というのは映画作りにおいて極めて発展的な手法で、手を出すのは「視聴者が理屈抜きで十分に楽しめる物を作る」という最も基本的なステップを踏襲してからがいい。映画に含まれたメッセージは観客が前のめりになっている時のみ探し当てて貰えるし、受け取って貰える。ほとんどの観客は映画を純粋に楽しみに来ているのであって監督の説教を聞きに来ている訳ではなく、そういう意味でも西野は初監督作品である本作で、まず観る者を最大限楽しませることに注力すべきだったのだ。
例えば近い時期に公開された「シン・エヴァンゲリオン劇場版」で碇ゲンドウが「その時々で人は違うことを言う・多分どちらもその人には本当なんだろう・そのときの気持ちが違うだけだ」と独白するシーンがあるが、これは作品を世に投げる度に時には酷くなじられ、時には絶賛を浴びた監督自身の主観的な意見と汲む事が出来る。作り手の主張というのは本来この程度、作品を気に入って何度もリピートする人や深く考えながら鑑賞したい人だけが気付くレベルに留めるのが丁度良く、そうでなければ物語の本筋への没入を削いでしまう。人間に絶望したゲンドウはどんな選択をし、希望を与えてくれたのは誰だったのか、ゲンドウが監督自身の投射だとすれば監督にとってそれは誰なのか、等と考えるのは通な人用のオプションとして配置しておくべきなのだ。
西野は20代も前半の若い頃から自分好みの理想論を、声高に語るのが好きだった。芸人を志したのは聞き手に向けて一方的に話せる仕事で、世の中に多大な影響を誇るカリスマになり得る仕事だったからに他ならない。それが当たらずで絵本やサロンに手を伸ばしたのも、全ては自分を才気溢れるカリスマとして演出し、自分の理想通りに動く世界を作る為である。
西野はお笑いも絵本も映画も、海外に学校を建てる事も別に好きではないのだ。自身をカリスマにし得る物なら何にだって手を出すだろう。芸人だった頃も映画監督である今も、見る側の事など端から眼中にない。みんな俺より劣ってんねんから黙って従っときゃええねん、というのが彼の本音なのだ。
彼にとって、例えば松本人志や宮崎駿、イチロー等は理想の人に当たると思うが、誰もそんな精神性で仕事に取り組んでいないし、生まれ持った素質で今の地位に就いている。
お笑いや映画は感受性に乏しく、独善的で受け手の立場に立てない西野には全く向かない分野で、彼は目標の設定も達成するまでの道程も全て間違えているし、センスが無くてこういった分野で成功出来ない事をどうしても認めたくなく、しがみついているような状態だ。
映画の本筋は「空に浮かぶホシ、という実際にはあるかないか分からない物を見つける」という物で、「広大な空のどこにあるか分からない、実態が分からず実在も怪しい天空の城を探す」という「天空の城ラピュタ(1986)」の超絶劣化版で、それにワンピースの千番煎じのようなキャラデザ、演出を加えたのが「えんとつ町のプペル」である。
作中延々繰り返される「星はある」「星はない」の議論に観客はいちいち「いやあるだろ星は」という感想しか持てず、「星があるかもって考えたらドキドキするよね」に対しては「いやしないです」と思うしかない。
「あるかないか分からないがあるとしたら胸が高鳴る、それに向かって挑戦する姿は素晴らしい」というメッセージ性を成立させたいなら観客が西野に目線を合わせに行かなくてもそう感じるような題材を選ぶべきで、星みたいなありふれた物や、町を覆う煙を何とかする、みたいな要素ではどうにもならない。それが分からないのはセンスや思想の違いではなく単なる勉強不足だ。
この映画を何度もリピートしていて毎回終幕と共にスタンディングオベーションをしているような人達は西野のファンで、初めから西野に目線を合わせに行っている。本作は西野のファンしか感化出来ないような内輪向けの作品で、西野本人がそこに思い至っていない様子は見ていて痛々しい。
本作は序盤から超展開の連続で、西野が「こうなればいい、こうなって欲しい」と思う方向へ説明や前フリを大幅に省いた雑な展開で進んでいく。主人公を自分、町民達を世間に例える構図で進めるつもりが「革新的な施策を思いつくも、世間からバッシングを浴び狭い範囲に引き籠もり、嘘と目隠しで理想の世界を作り、異を唱える者には攻撃を加える」という異端審問官の方が西野に似てしまったのは盛大な皮肉である。冷静で丁寧な製作を心掛けないからこういうミスを犯すのだ。
西野亮廣はとにかくセンスが無い。その源となる感受性や人格の柔らかさに乏しく、創作物の作り手としては絶望的だ。芸人時代に作ったネタも絵本も映画も、センスを生かさなければならない部分は全部誰かの流用コピーに頼っている。
西野のようなタイプは数的記録やトロフィーの数に挑戦し続ければ本領発揮出来るのだが、彼はそれが嫌なのだ。自分がセンスの人でありカリスマ性で人を惹き付けている事にすべく剛腕で現実を捻じ曲げようとしているが、その姿はあまりに異様で、彼の目指す理想像とはどんどんかけ離れて行っている。彼はそれをどうしても「純粋な挑戦」と世間に認めさせたくて自分とルビッチをなぞらえている訳だが、まだ見ぬ物を探求する心と自分の理想にネチネチと執着するのとでは訳が違う。作中「俺は悪くない。誰にも迷惑はかけてない。責められる謂れは無い。」という主張を展開するがそんな言葉を使って自分を守らなければならないチャレンジャーがどこにいるものか。彼だって本当は自分のやっている事が後ろ指を指されるような事で、既に負けた勝負の上でしつこくゴネているだけだという事を分かっているのだ。
西野は今後も思考力が弱く、明るければ何でもよく見えてしまう人々を集めて局地的なカリスマで居続けるだろう。それは現実社会に疲れ果て、行き場を無くした人々を囲い込む新興宗教団体と同じ運営方式だ。その点を突っ込まれることが嫌ならさっさと世の中全てが違和感を覚えず自分も最大限納得出来るような活動形態を作り出せばいいだけなのだが、何しろ彼は人より多めに努力が出来るだけのセンス無しだ。今後もそんな気の利いた真似は出来ないだろう。